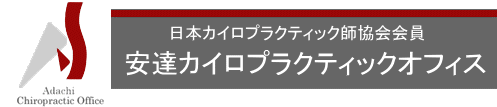起立性調節障害について学びました。
-腰が痛い、肩がこる、頭が痛い、身体がだるい、めまい、自律神経失調症、顎関節症、便秘、生理痛など・・・でお困りの方、長岡で唯一、カイロプラクティックと鍼灸の長所を生かした施術ができる当院におまかせ下さい-
3月2日(土)の夜に毎月第一土曜に行われる「分子栄養学」の勉強会に参加しました。
今回は子どもと栄養というタイトルで、起立性調節障害をはじめ、アトピーなどいろいろな病態へのアプローチの仕方を学びました。
子どもの体調不良・学校にいけないという場合に、起立性調節障害(OD)による体調不良が考えられます。
起立性調節障害は、思春期に好発する自律神経機能不全の一つと考えられます。症状としては、①立ちくらみ、②朝起きられない、③朝弱いが夕方になると元気になる、④やる気が出ない、⑤身体がだるく、疲れやすい、⑥睡眠障害、⑦頭痛、肩こり、⑧動悸・頻脈、⑨胃腸の不調など様々です。
有病率は、軽症例を含めると、小学生の約5%、中学生の約10%となり、不登校の原因の約3~4割程度に起立性調節障害が関係していると考えられています。
原因としては、●起立に伴う循環動態の変動に対して、自律神経による代償機構機能しない ●過少または過剰な交感神経活動、●水分、塩分の摂取不足、●心理・社会的ストレス、●日常の活動量低下などがあります。
起立性調節障害の改善のための考え方としては、
☆脳と副腎の働きに問題がある、HPA軸機能障害(副腎疲労症候群)に対するアプローチ
☆成長期の子ども特有の身体のアンバランスに対するアプローチ
・急激な身体変化が起こるため、自律神経のバランスが崩れやすく、脳や心臓への血流低下が起こりやすいので、その改善に対するアプローチ
・急な成長によって、鉄や亜鉛不足が起こりやすいので、栄養面からのアプローチ
・副腎や甲状腺などの内分泌臓器の働きも考慮
☆心理社会的、化学的ストレスなどからくる身体への影響も考慮したアプローチ
などが改善の方向性となりますが、その人その人で異なりますので、個別にみていくことが大切となります。
日常生活での注意点については次回お話いたします。